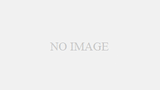直方体の見取り図の書き方
簡単な見取り図の書き方を紹介する。
1 ノートに長方形を一つかく。始めは長さを指定した方がいい。
縦3cmで横4cm程度が書きやすい。
2 1個目とは少し斜めにずらして、全く同じ大きさのものを書く。
3 頂点同士を定規でつないで出来上がり。
子どもたちはけっこう驚く。
2回目は、反対側の斜めにずらして同じように書かせる。
ここからは作業時間に合わせてさまざまな課題を出すといい。
実際には見えない辺は薄く書かせる、点線で書かせる、消すなどの方法を採らせてみる。
また、見えない部分を消させるのだが、一部を描くと「ふたの空いた箱」に見える。こうしたものも書かせてみる。
そこまでできたら、大きさを自由に変えて書かせてみてもいい。自学にも使える。
この作業は厳密にいうところの見取り図にはならない場合もある。(奥行きを表す辺の角度は決まっている)しかし、教科書やテストでは、そこにこだわるせいで、作図が中途半端の課題ばかりなのである。
こうした作業は、社会科で日本地図をおおよそ描ければいいという発想とよく似ている。
自学などでどうしても立体の図が必要な時に、さっさと描ける方法が一つあれば、子どもたちの思考も無理なく進むだろう。