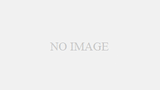6年線対象の指導
算数の学習は定義から入る方がシンプルな場合がほとんどだが、定義をあとから追いかけさせる方がいい時もある。線対象の指導は、その一つである。
教科書の場合は、二つに折って重なる図形を見つけさせる。
今回は先に作図させてみる。
「二つに折って左右がぴったり重なるような形がありますよね。これを線対称な図形といいます。」とさらっと説明して「線対称」とノートに書かせる。漢字を間違うので、出会いから気をつけさせる。
「では、これから時間をあげますので、自由に線対称の図形を書いてください。」
「折り目になる線を一本引きます。(対象の軸という言葉は後から教える。)半分に自由に書いてください。そして、自分が書いたものの残り半分を正確に書いてください。」
そしていくつか例を挙げるといい。
初めは長方形や三角形を書く子どもが多いだろう。中には初めから飛行機や城などを書いたり、自分で幾何学模様を書いたりする。
線対称の図形は、感覚的に分かりやすい。「対象に軸に対して、対応する点を結ぶ線は直角に交わる」など知らなくても書くことができる。
だから書かせることで体験を増やしていく。一定時間が過ぎたら、友だちと見せ合いをしてもいい。
さらに、対象の軸を横向きにするとどんな図形ができるか、さらには斜めにしたらどんな図形ができるかなと教師が全体に声をかけていくといい。
ノートにはマス目があるので、今回はそれを大いに活用できる。
このような活動では、一度子どもたちに自由に思考と活動をさせると、その子どもに見合った内容で習熟を重ねることができる。複雑な図形を初めから書ける子どもと、単純な図形で終わっている子どもも同時に活動ができる
そのあとで交流させることで視野を広げさせる。おもしろいと思ったものはどんどんまねさせる。始めに自分なりの蓄積をしているから、友だちからの情報も入りやすい。
一通り終わったところで「対象の軸」という言葉を教え、自分の書いた図形に、それぞれ赤鉛筆で対称の軸を書き込ませ、漢字で書かせるとさらに習熟できる。