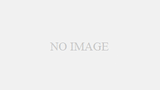走り幅跳び3
跳んだときに体がふわっと浮くような感覚を体感させる。それは、高いところから飛び降りたりトランポリンを跳んだりするような感覚とは少し違う。
走り幅跳びでは助走がある。垂直に跳ぶわけではない。助走からの跳躍に角度を生み出すためにふわっと上がる感覚をまず知ってもらうのである。
そのために、私も段ボール箱のような障害物を置いてみたこともあったが、跳び越えるだけになり、むしろ距離が伸びなくなった。
跳び箱の踏み切り板を使ってみた。これがよかった。しかも踏み切り板を2枚重ねておくという方法を採った。
助走を跳躍に変えるときの跳躍の進入角度を、踏み切り板によって半ば強制的に変えるのである。
子どもたちに跳ばせると、初めはびっくりする。ほんとうに浮いたような感覚になるからだ。だからまずゆっくり助走して感覚になれてもらう。
何度か跳んでいるうちに、ふわっと浮いている感覚がつかめてくる。これをそのままやりすぎると、たしかにふわっとは跳ぶのだが、距離を延ばすことに意識が行かなくなる。ただ跳んでしまうだけになる。
助走のスピード上げ、太ももを引き付けて跳躍することで前に跳ぶことを意識させる。
いわゆる「走り幅跳びの跳び方」にフォームを変えていくのである。
ある程度慣れてきたら、踏み切り板を1段にする。そして「自分の跳躍の力で、さっきと同じようなふわっとした感覚を創り出してください。」と指示する。
先に指示したように太ももを体に引き付けるような跳び方を身につけることで跳躍の角度を上げていくようにするのだ。
こうなると、子どもたちの跳び方も少しずつ変わってくる。時々に感覚を取り戻すために踏み切り板2枚に戻りたい子どもも出てくる。
そこで、砂場は、①踏み切り板2枚②踏み切り板1まい③踏み切り板なし、という3つの場が作られることになる。
慣れてきたら、本来の走り幅跳びのように、何も補助のないフラットな場所での跳躍に戻していく。ここまでが第1時である。