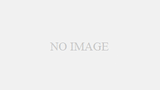走り幅跳び2
走り幅跳びの「原初的なおもしろさ」
走り幅跳びの跳躍に高さを生み出すことの必要性を述べた。これは物理的な法則によって説明ができる。いわゆる弾道の問題である。一定の速度と高さによって、物体は遠くまで飛ぶことができる。
走り幅跳びも、助走のスピードはもちろん大切だが、跳躍の高さ(つまり角度)を創り出すことで跳躍の距離を延ばすことに工夫のポイントがある。
・・というようなことも、まず子どもたちは知らない。だから、ほとんどの子どもは助走が速ければそれだけ遠くに行けるはずと思っている。そして、遠くに跳ぶのだから前に跳ぶのが当然だと思っている。前に跳べば、高さは出ない。それでいいと思っている。高さが必要だという思考にはならない。
まずはボールを投げるなどして、角度と距離の関係を見せる。同じ力で投げても、向きによって着地点が変わることはすぐに分かる。
これが「幅跳びのコツですよ。」と伝えなければならない。これが第一歩である。
しかし、原理が分かったからといって、全員がそのように跳べるのであれば、こんな楽なことはない。ボールを投げるのは手をコントールすることで、まだ簡単である。(ちなみにこんなことでも低学年には難しいが。)
走り幅跳びは、自分の体そのものの跳躍の角度を上げていくのである。これをコントロールするのは相当に難しい。
角度が上がっているかどうかをメタ認知するのが難しい。真上に上がるならまだわかりやすいが「適度に角度を上げる」というようなことの方が難しいのだ。角度は上がったのか、上がったとしてこの角度でいいのか、子どもたちには実感がつかみにくい。
そして何より、頭で角度が必要だと思うことと、実際に跳ぶならやっぱり前に跳ぶ方が距離が延びる感じがすることのずれを解消できないままである。
子どもたちに高さを生み出してもらうようにするためには別の方法が必要だ。
子どもたちの感覚に訴えるのである。
つまり角度という論理的な思考よりも、「ふわっと」浮くように跳ぶ、と感覚をつかんでもらう方が分かりやすいのである。ここに走り高跳びの「原初的なおもしろさ」がある。